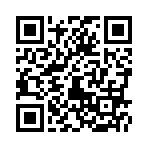2012年03月26日
カルタゴ興亡史。
子供の頃、太平洋戦争の話を聞いたとき、自分のなかではものすごく昔の出来事という印象でした。 今から思うと私が生まれるほんの30年ほど前の出来事なのですが、5~10歳程度の子供にすれば 自分の生涯を越える年月に対して実感が湧かなかったのでしょう。 私は30歳をすぎてからある程度、時間の尺度が把握できるようになった気がします。 300年前は自分の人生の10回分前か、というふうに。 しかし、これが2000~2500年前とか言われると話は別。 もう想像できないくらい遠い昔。 そんな時代に繁栄した都市、カルタゴがありました。 現在のチュニジアのあたり。 もともと東部地中海地域のフェニキア人が貿易都市としてアフリカ大陸に構えたようですが、 商魂たくましいカルタゴはみるみるうちに商圏を拡大、本国を上回るほどの富を得ました。 初期の頃は勢力争いをギリシャと繰り広げ、シチリアなどでよく軍事衝突がめまぐるしくあったようで すが、その都度和解し相互の勢力地図を塗り替えていました。 その後、ローマの台頭により今度はこちらの方に軍事作戦を展開せざるを得なくなります。 結果としてポエニ戦争(第一次~三次)を経て、カルタゴはローマに滅ぼされてしまいます。 カルタゴは当時、財力もあり、文化度も高く市民生活はローマのそれと比べて非常にレベルの高い ものでしたが、それが逆にローマの反感をかったのかもしれません。 カルタゴの軍隊も充実しており、名将ハンニバル率いる精鋭はイベリアからはるかローマまで、 険しいアルプス山脈を越え、ローマを10数年翻弄し続けたこともあります。 ですので、けっして経済だけの弱小都市ではありませんでした。 ただ軍隊構成は、統制する要職はカルタゴ人でしたが兵隊はほとんどいつの戦いも傭兵部隊が主。 このことから「自分たちで自分たちの生命・財産を守る」という意識は希薄だったかもしれません。 「カルタゴ興亡史」 松谷健二氏著 を読んで私が感じたことは、新しく台頭してきた都市や国は、その上昇志向と旺盛な支配欲に 後押しされ、力ずくで相手をねじ伏せ、それを踏み台にしてのし上がっていく、 そこでは冷静な判断は疎ましがられ、勢いで突き進んでいく、 一旦敵とみなすと、相手の言い分などは関係ない、とことん相手を駆逐することに邁進する、 ということ。 これは古代ローマに限らず、人間の本質にかかわるもののように思います。 この時代のカルタゴに日本の将来がだぶって見える、という方も多くおられますが私もその一人。 商売上手で経済的にも隆盛を向かえた。生活レベルは高く、ある程度お人よし。 市民は自分たちの利害には敏感だが、都市間の折衝にはあまり興味がない。 戦時には市民の安全は傭兵に守って(戦って)もらう、など。 そして強大な力をもって台頭してくるローマは、現在では中国という印象です。 あてはめて想像するとまさに古代の状況が現代に蘇ってくるように感じるのは私だけでしょうか。 興味のある方はご一読あれ。 つづく
Posted by duqhsxthkc at 13:55│Comments(0)